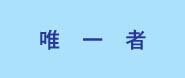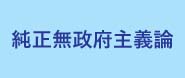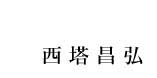何故、心霊無政府主義なのか
私は、大正時代の印刷工アナーキストが一番好きだった。彼らが、五十年後にも、まだ若かった我々に強調していたことは、自分たちは日常生活で相互扶助を実践していた、だからアナーキストになったんだということであった。その相互扶助とアナーキズムの結びつきの直線性・単純性がすごく好きだったのである。スピリチュアリズムとマルクス主義、スピリチュアリズムとアナーキズムでは、スピリチュアリズムとアナーキズムの方が親和性は高いといえよう。マルクス主義の唯物論についての質問に、シルバーバーチ霊は直接答えず、共産主義について「私はラベルというものにはまったく関心がありません。私にとっては何の意味もありません。地上世界ではラベルが大切にされます――共産主義者、社会主義者、保守党、労働党、スピリチュアリスト、セオソフィスト、オカリスト、等々、挙げていったらキリがありません。しかし、大切なのはラベルではなく、その中身です。コミュニストという用語の起源は、物的財産は共有するのが正しいと信じた遠い昔にさかのぼります。それ自体はとても結構なことです。いかがでしょう、有り余るほど持っている人が足りない人に分けてあげるというのは公正なことではないでしょうか。…分かち合うというのは立派な原理です。…みんなで分け合うという理念は結構なことです。共産主義という用語そのものに怯えてはいけません。初期のクリスチャンには全財産を共有し合った時期が、少しの間でしたがありました。ということは彼らのことをコミュニストと呼んでもよいことになります。一つの理念をもつことと、それを実現するために拷問や抑圧や迫害や専制的手段を用いることとは別問題です。そこに大事な違いがあります。」と答えており、また「もしコミュニズムが真の協調性を意味し、階級上の差別もなく、住民がお互いに助け合う心をもった社会のことであるとすれば、現在の地上世界で思想的にコミュニズムを標榜している国家には、そういうものは存在していません。」(以上『シルバー・バーチの霊訓11』)とも述べている。相互扶助はアナーキズムの強調するところであり、また共産主義実現のための強権的な手段をアナーキズムも否定する。また、自由と自由意志を強調するところ、社会をあくまでも個人の集まりとして捉えるところなども、スピリチュアリズムとアナーキズムで共通するといえよう。もっとも、大多数のアナーキストもマルクス主義と同じように唯物論者であるといえる。ただ、シルバーバーチ的には唯物論か霊や死後の世界を認めるのか、無神論か神の存在を認めるのかといったことはどうでもいいことであり、他者への奉仕、他者のために何かしているかどうかだけが大切であり、アナーキズムに対して言えばアナーキストがその相互扶助を実践しているかどうかが重要だということになる。
心霊無政府主義とは何かということであるが、おそらくそのようなものが社会にあるわけではなく、自分の中にあるだけだといってもいいであろう。では、何故心霊無政府主義かといえば、スピリチュアリズムと出会い、それを受け入れたからである、しかし、それなら単にスピリチュアリズムでいいのではないかということにもなるが、心霊無政府主義を名乗るのは自分がアナーキストだったからとしかいえない。アナーキズムへのこだわりがどうしても抜けず、アナーキズムとスピリチュアリズムの間を揺れ動いているのである。スピリチュアリズムに出会う以前、自分はアナーキストとシュティルナー的唯一者との間を揺れ動いていた。スピリチュアリズムに出会うことにより、今度はアナーキストと唯一者とスピリチュアリストの間を揺れ動くということになったわけである。ではそのような動揺の中で何故心霊無政府主義なのかといえば、スピリチュアリズムとアナーキズムの親和性がある。シュティルナーはアナーキストの一人として語られることも多いし、スピリチュアリズムよりアナーキズムに受け入れられているといえるかもしれないが、もしかしたらアナーキストとスピリチュアリストの間の距離より、アナーキストと唯一者の距離の方が大きく、スピリチュアリストと唯一者との距離はさらに離れているかもしれない。さらにいえば、スピリチュアリズムと唯一者の関係は、自我の主体性という点でのみ一致するだけで ――スピリチュアリズムでは自我の霊性進化に関していえるだけであるが――、相反する関係にあるようにもみえる。
心霊無政府主義には無政府主義という言葉が入っているけれど、共産主義と無政府共産主義が違うように、アナーキズムと心霊無政府主義とは別物であると考えている。ただ、それは絶対的なものではなく、あくまでも自分としてはということである。無政府共産主義がアナーキストの共産主義であるように、心霊無政府主義をスピリチュアリストの無政府主義という意味で使っているともいえる。スピリチュアリズム的にはどうでもいいことであるが、アナーキズムと心霊無政府主義の区別を求めているのは、私の中のアナーキズムなのである。アナーキストとしての自分にとって重要なことはアナーキズムとは主体的思想であるということであった。それ故、自分にとってアナーキズムとマルクス主義はまったく別の思想であったし、同じように、アナーキズムとスピリチュアリズムは違うものであり、アナーキストでありかつスピリチュアリストであるという二股的立場は否定されなければならないものとしてあるわけである。おそらく、大部分のアナーキストもそのことに同意するであろう。もちろん、例えばイエスもアナーキストだという言い方をするアナーキストもいる。しかし、自分は主体的にアナーキズムを選んでいる、それゆえ自分はアナーキストなのだという意識が強ければ強いほど、そのような自分をアナーキストと自称してもいない人間をアナーキストとみなしていくという、いわば相手の主体性を無視した姿勢自体を否定することになるであろうし、主体的なアナーキストであろうとすればするほど、アナーキストでありスピリチュアリストでもあるというような曖昧な立場は認められないということになるわけである。アナーキズムの多様性を考えかつ教条主義を避けようとすれば、各人の主体性に依拠せざるをえなくなるともいえる。自分がアナーキストと考えるなら、その人間はアナーキストなのだということにせざるをえなくなるわけである。逆にいえば、自分でアナーキストと思っていない人間は、その考えがいくらアナーキズムに近いといってもアナーキストと認めるべきではないということにもなるわけである。もっとも、スピリチュアリズム的にはラベルに拘らないということなのであるから、アナーキズムの中にスピリチュアリズムを取り入れていくのも、スピリチュアリズム的には何の問題もないということになるから、スピリチュアリズム的なものを自己のアナーキズムに取り入れたアナーキストというものが出てくることは当然ありうる。将来的にそのようなアナーキスト・スピリチュアリズムを標ぼうするアナーキストが出てきたとき、自分とそのようなアナーキストを区別する必要もないであろう。
自分がアナーキストではなくスピリチュアリトであるというのは、アナーキズムよりスピリチュアリズムの方が上だと思わざるをえないからでもある。少なくとも、他者のためにな何かしよう、相互扶助を実践しようという思いは、アナーキストよりはスピリチュアリストの方がはるかに強いということはいえるであろう。とはいっても、アナーキズムをスピリチュアリズムの視点から捉え直してみたいという思いもあるのである。心霊無政府主義とは相互扶助的アナーキズム、相互扶助を何より強調したアナーキズムといってもいいのかもしれない。シルバーパーチも、「地上人類が救われる道は互助の精神を実践することそれ一つにかかっおり、それ以外にはないのです。…互助のないところには荒廃があるのみです。互助のあるところには平和と幸福があります。地上世界も互助の精神によって新しい秩序を生み出さないといけません。」(シルバーバーチ『愛の摂理』)と述べている。相互扶助のみが新しい、より完成した社会を作っていくのである。アナーキストの意識が変化するにしたがい、その方向に落ち着いていくという可能性もある。心霊無政府主義とアナーキズムを一応区別したけれど、その区別性は曖昧になっていき、結局、心霊無政府主義もアナーキズムの一種ということになつていくかもしれないが、それは心霊無政府主義にとっては否定的なことではない。相互扶助に立脚したアナーキズムは、それをお題目のように唱えているだけでなく、その実践を絶えず意識していくなら、霊界からの支援が期待できるということでもある。宇宙最大の勢力と同盟を結べる可能性があるなら、圧倒的少数者としてのアナーキストとしては、その可能性を考えてみる価値はあるような気がするし、頑なに唯物論的立場に固執することもないのではないだろうか。
スピリチュアリズムの立場から心霊無政府主義をみるなら、シルバーバーチ霊は「主要道路だけでなく、横道に入ってみることも、これから大いに要請される仕事です。」(シルバーバーチ 『愛の絆』P174)と言っている。心霊無政府主義はスピリチュアリズムの主要道路ではないであろう。しかし、横道という事はあるかもしれない。また、シルバーバーチ霊は「大霊は人間のすべてに一定範囲内の自由意志を授けてくださっています。あなたは操り人形ではないということです。知性があり、理性があり、判断力・決断力・反省力を有し、自分の意見を主張し、人生体験によって叡智を身につけていくことができます。」(『シルバー・バーチの霊訓12』 P86)ともいっている。また、『ベールの彼方の生活』でも「こちらの世界では誠意さえあれば、たとえその教えが間違っていても、間違いを恐れて黙っているよりは歓迎されるのです。」(『ベールの彼方の生活』第一巻P186)と言われている。自分の述べていることは間違っているかもしれない。ただ、霊界だけでなくこの世においても、間違っていても自分の意見は発表すべきかもしれないわけである。